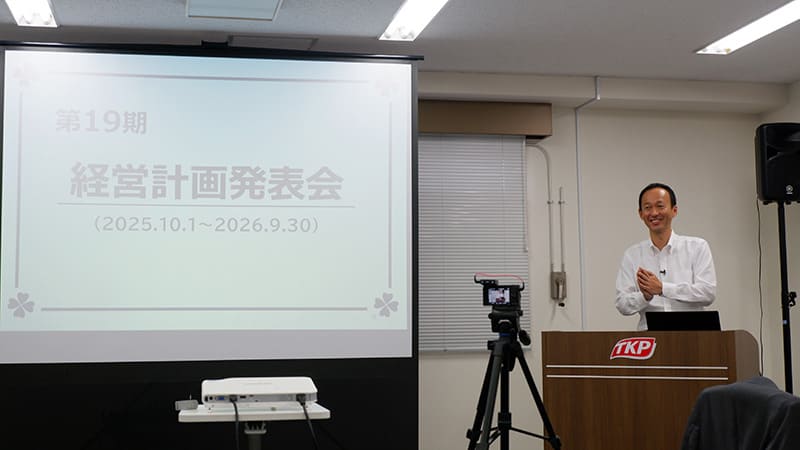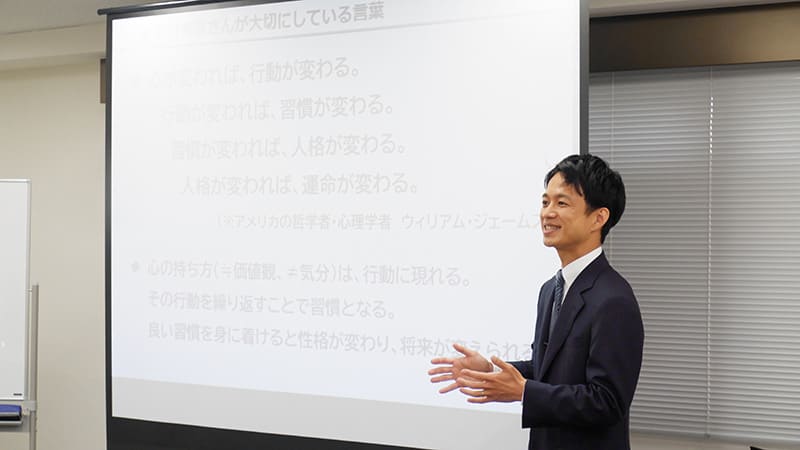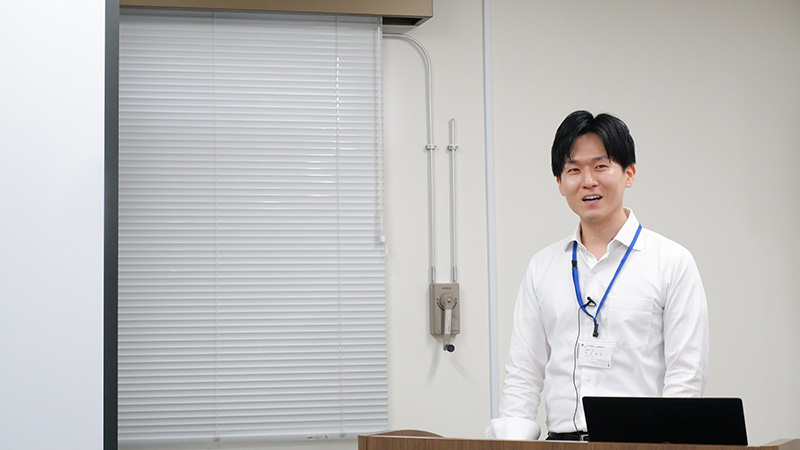明らかに問題がある仕事をしない従業員への対応方法
- Vol.198
- 2025年11月号

- 目次
- 「法律コラム『明らかに問題がある仕事をしない従業員への対応方法』」
- 「第19期経営計画発表会報告」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
- 「お勧め書籍の紹介」
明らかに問題がある仕事をしない従業員への対応方法

1. 繰り返しの注意・指導
従業員を有効に解雇するためには、法律上の厳しい要件を満たす必要があります。そのため、まずは、従業員に勤務態度を改めてもらうことを考えましょう。従業員は、そもそも自分の態度が問題だと思っていないケースがあります。勤務態度が悪いことを本人が自覚すれば、改善する可能性があります。
勤務態度を改めてもらう手段として、もっとも簡明なのが注意・指導です。「本当に改善してもらおう」と何度も熱心に繰り返し注意・指導を行います。始めは口頭で行い、それでも改善しなければ書面での注意に切り替えます。事案によっては日報を使って指導を行うケースもあります。仮に改善されなかったとしても、繰り返し注意・指導をした事実が、後の懲戒処分や退職勧奨の際に重要な根拠となります。
2. 懲戒処分を検討する
口頭や書面による繰り返しの注意・指導を行ったにもかかわらず、勤務態度が改善されない場合は、懲戒処分を検討します。始めから重い懲戒処分を科すと無効の可能性があるため、戒告や譴責などの処分から検討することになるでしょう。
懲戒処分は制裁罰であるため、慎重な手続きが不可欠です。就業規則を確認の上、問題従業員に弁明の機会を付与しましょう。 行為に対して処分が重すぎないか、過去の事例との公平性が保たれているかも含めて冷静に判断する必要があります。
3. 退職勧奨の実施
度重なる注意・指導によっても改善が見られない場合、選択肢の一つとして、退職勧奨により任意での退職を促すことを検討します。
従業員が退職の意向を示したら、その意思表示が明確なうちに退職届を提出してもらうことが重要です。退職届は従業員が自主的に退職したという証拠になります。退職届があれば、従業員から「解雇された」という主張が出てトラブルになるリスクを減らすことができます。
ただし、退職勧奨はあくまで従業員の自由な意思に基づく退職を促すものです。強要と受け取られることのないよう、従業員が冷静に判断するための時間を与えるなど、慎重な対応をしましょう。退職勧奨にはさまざまな注意点がありますので、当事務所のWEBサイトも併せてご参照ください。
(文責 弁護士 米井 舜一郎)
第19期経営計画発表会を行いました
10月1日に経営計画発表会を行いました。おかげ様で今年度で19期目に突入しました。これもひとえに皆様のお力添えのおかげでございます。いつも本当にありがとうございます。
さて、毎年恒例となっています経営計画発表会の様子をお伝えいたします。
経営計画発表会は前期の振り返りと今期・中長期的な将来の展望を事務所として、弁護士として話す機会となっています。代表が事務所全体の話をし、各所長などがそれぞれの担当部門の発表をいたします。話すテーマは同じですが、各弁護士個性あふれる発表となりました。
その他、所内の各業務グループからの報告・新入所員紹介・研修・生成AI勉強会等、丸一日かけた密度の濃い経営計画発表会となりました。
毎年のことですが、事務所・弁護士の目標を聞くことで所員全員一層気が引き締まり、同じ方向を向いて進んでいくのだと心がひとつになる実感があります。みなさまへより良いリーガルサービスをご提供できるよう、所員一同精進してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。最後は所員お待ちかねのお弁当タイムの写真で本記事を終わりたいと思います。
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー
早いもので2025年ももうすぐ終わります。そこで、今回は一足先に、2026年の新年の乾杯に向けて選ぶべきワインをご紹介します。
新しい年を迎える瞬間の乾杯は、一年の幸福と繁栄を祈る象徴的な儀式です。そのグラスに何を注ぐかで、その年の始まりの印象が大きく変わります。せっかくなら、味わいだけでなく「縁起」や「物語」を感じられる一本を選びたいものです。
スパークリングワイン
まず定番は、やはりスパークリングワイン。グラスの中で絶え間なく立ち上る泡は「希望」「発展」「喜び」の象徴で、世界中で新年の乾杯に欠かせない存在だそうです。フランスのシャンパーニュ、イタリアのプロセッコ、スペインのカヴァなどが新年にはおすすめです。

赤ワイン
一方で、穏やかで落ち着いた正月を過ごしたい方には、赤ワインが向いています。赤い色は古来より「生命力」「情熱」「厄除け」の象徴で、年の初めに飲むことで活力をもたらすそうです。
ぶどう品種メルロー主体のワインは柔らかく、煮物やおせち料理の旨味ともよく調和します。

ラベルに注目するのもおすすめ
太陽や星、黄金、幸運を意味するラベルを持つワインは、年始の集まりにぴったりです。ラベルからワインを選ぶのもよさそうです。

2026年を良い年にしたいという想い
新年の最初の乾杯には、その一年をどのように生きたいかという「願い」を込めたいです。
家族を含めて皆様の健康を第一にして、グラスを合わせる瞬間に「良い年になりますように」という気持ちを共有したいですね。
(文責 弁護士 大澤 一郎)
― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 『世界トップ1%の「聞く力」』 牧野 克彦 著
今月の「人生を元気で豊かにするお勧めの書籍」を、弁護士の大竹裕也がご紹介いたします。
今回ご紹介させていただくのは、牧野克彦氏の著書である『世界トップ1%の「聞く力」』です。
1. 著者の紹介
本書の著者である牧野克彦さんは、自動車ディーラーや生命保険の営業として30年以上活躍された方です。特に生命保険の営業においては、世界でトップ1%の成績を残した方だけが参加できる世界組織「MDRT」の基準を17年間連続で達成し続けたという、凄腕の営業マンです。生命保険会社を退職して起業・独立した後も、保険・金融業界において多くのトップセールスマンを育て上げたという実績をお持ちです。
著者は本書の中で、営業として良い結果を出すためには、商品の説明を丁寧に行うことよりも、顧客の不平不満を聞き出すことが重要だと述べています。
2. 特に印象深かった内容・フレーズ
本書では、「聞く力」というテーマをあらゆる視点から分析し、解説しています。その中でも、私が特に印象に残った内容やフレーズをいくつかご紹介します。
(1) 人は「信頼できる相手」から商品を買いたがる
筆者は、高度経済成長期のような時代と異なり、現代は身の回りに十分すぎるほど物が揃っていると主張します。このような観点から、現代人は物がほしいのではなく「満足」を求めており、最終的には「何を買うか」ではなく「誰から買うか」というところに行き着くと解説しています。
相手の不平不満をしっかりと聞き出し、真のニーズを掘り起こすための聞く力を磨くことで、お客様にとって「信頼できる相手」になれるのです。
(2) 心を読むな、聞いてしまえ
「相手の気持ちになって考える」、「相手の立場に立って行動する」といった、よく耳にするコミュニケーションがうまくいく秘訣について、筆者は否定的な見解を示しています。
「相手の気持ちは聞かなければわからないのだから、だったら聞いてしまえ」というのが筆者の主張です。
電車で高齢の方に席を譲ろうと声を掛けたら「そんな歳ではない!」と怒らせてしまった場合のように、勝手に相手の気持ちを推測して行動してもうまくいかない場面が多いものです。そのような事態を避けるためには、率直に相手が何を考えているのか、何がしたいのかを聞いてしまう姿勢が大切だとのことです。
(3) 「迷う」のは興味がある証拠
「人は全く興味がないものには迷わない」と考えてみれば当然のことですが、あまり考えたことのない発想にはっとさせられました。
そして、迷っている相手に対して必死に説得しにかかることは、かえって逆効果になるそうです。
相手が迷うくらいに魅力を感じているのだからこそ、何に対して不安などを抱えているのかをしっかりと聞き出し、それを一つずつ解消することが相手からイエスという回答を引き出すために重要なのです。
3. おわりに
今回は、「聞く力」をテーマにした本書をご紹介させていただきました。人は生きていれば他人と話し、話を聞く場面があります。営業のお仕事をされている方だけでなく、どんな人にもコミュニケーションに役立つノウハウがたくさん詰まっていますので、ぜひ一度手に取っていただけたら嬉しいです。
(文責 弁護士 大竹 裕也)